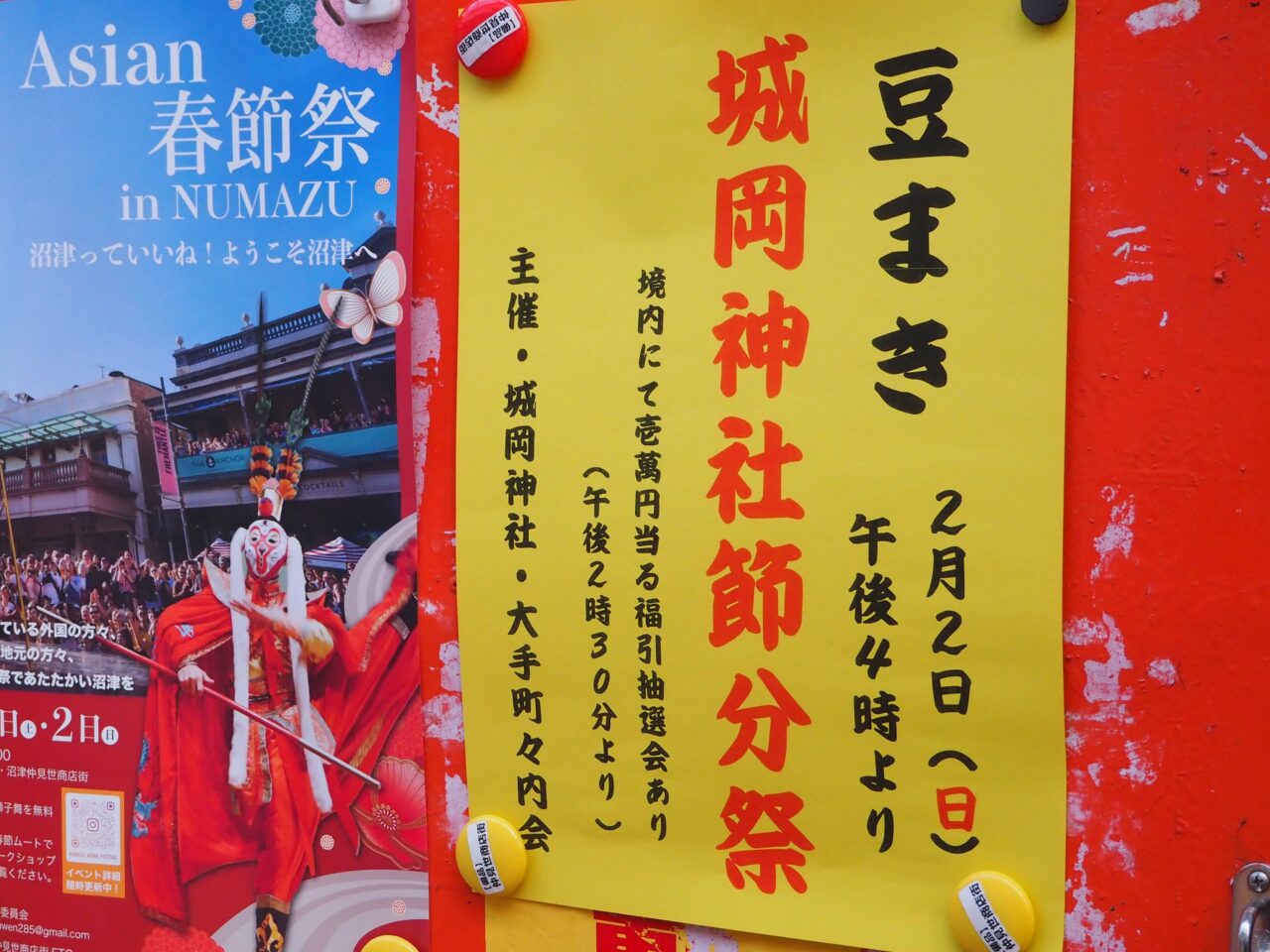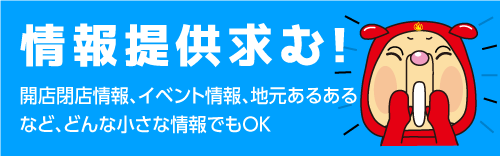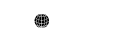【沼津市】タカアシガニの放流が戸田湾沖で実施されました
 毎年5月の恒例行事となっているタカアシガニの放流が、2025年5月16日(金)に戸田湾沖の海上で実施され、地元の戸田小中一貫校の児童・生徒たちが参加しました。子どもたちは実際にタカアシガニに触れ、タグ(標識)付けや計測、さらに漁船で沖合に出ての放流作業までを体験しました。
毎年5月の恒例行事となっているタカアシガニの放流が、2025年5月16日(金)に戸田湾沖の海上で実施され、地元の戸田小中一貫校の児童・生徒たちが参加しました。子どもたちは実際にタカアシガニに触れ、タグ(標識)付けや計測、さらに漁船で沖合に出ての放流作業までを体験しました。
 タカアシガニは世界最大級のカニであり、沼津市・戸田地区の特産品として知られています。水深150〜800メートルの深海に生息していますが、駿河湾はプランクトンやミネラルが豊富で水温も年間を通じて安定していることから、戸田沖では質の高いタカアシガニが漁獲されています。しかし近年は漁獲量が減少を続けており、生態の解明や資源保護を目的とした放流が、1986年(昭和61年)から毎年行われています。
タカアシガニは世界最大級のカニであり、沼津市・戸田地区の特産品として知られています。水深150〜800メートルの深海に生息していますが、駿河湾はプランクトンやミネラルが豊富で水温も年間を通じて安定していることから、戸田沖では質の高いタカアシガニが漁獲されています。しかし近年は漁獲量が減少を続けており、生態の解明や資源保護を目的とした放流が、1986年(昭和61年)から毎年行われています。

タカアシガニに関する講話を行う沼津市商工会の中島寿之さん
作業前には、タカアシガニに関する講話が行われました。タカアシガニの成長は非常に遅く、平均寿命は30年ほどと推定されていますが、中には100年生きるのではないかという見解もあるそうです。また、タカアシガニには「定着型」「移動型」、さらには「駿河湾を出入りする広域移動型」の3種類があるとされ、過去には戸田でタグ付けして放流された個体が、遠く三重県熊野灘で再捕獲されたという例も紹介されました。
 講話を終えると、さっそくタグ付けと計測作業に入りました。タグは3番目の足に、結束バンドを使って固定します。
講話を終えると、さっそくタグ付けと計測作業に入りました。タグは3番目の足に、結束バンドを使って固定します。
 タグを付けたあとは、性別、卵の有無、甲羅の大きさ、重さなどを記録しました。中には自分の顔ほどもある大きなタカアシガニを抱える生徒もいましたが、皆さんはとても手慣れた様子でカニに触れていました。
タグを付けたあとは、性別、卵の有無、甲羅の大きさ、重さなどを記録しました。中には自分の顔ほどもある大きなタカアシガニを抱える生徒もいましたが、皆さんはとても手慣れた様子でカニに触れていました。

御浜岬から沖へ出る漁船
記録作業を終えると、漁船に乗って沖合へと向かいました。港からおよそ1.2キロメートル離れた、水深120メートルほどの地点が今回の放流場所です。
 子どもたちは放流にあたって「元気でね!」と声をかけ、深海へと潜っていくタカアシガニたちに手を振って見送りました。今回は合計41匹のタカアシガニが放流されました。
子どもたちは放流にあたって「元気でね!」と声をかけ、深海へと潜っていくタカアシガニたちに手を振って見送りました。今回は合計41匹のタカアシガニが放流されました。
 地域の食文化を学び、実際にタカアシガニに触れ、海に出て放流を体験する――。地域の将来を担う子どもたちにとって、かけがえのない一日となりました。
地域の食文化を学び、実際にタカアシガニに触れ、海に出て放流を体験する――。地域の将来を担う子どもたちにとって、かけがえのない一日となりました。
タカアシガニの放流が行われた戸田港はこちら↓