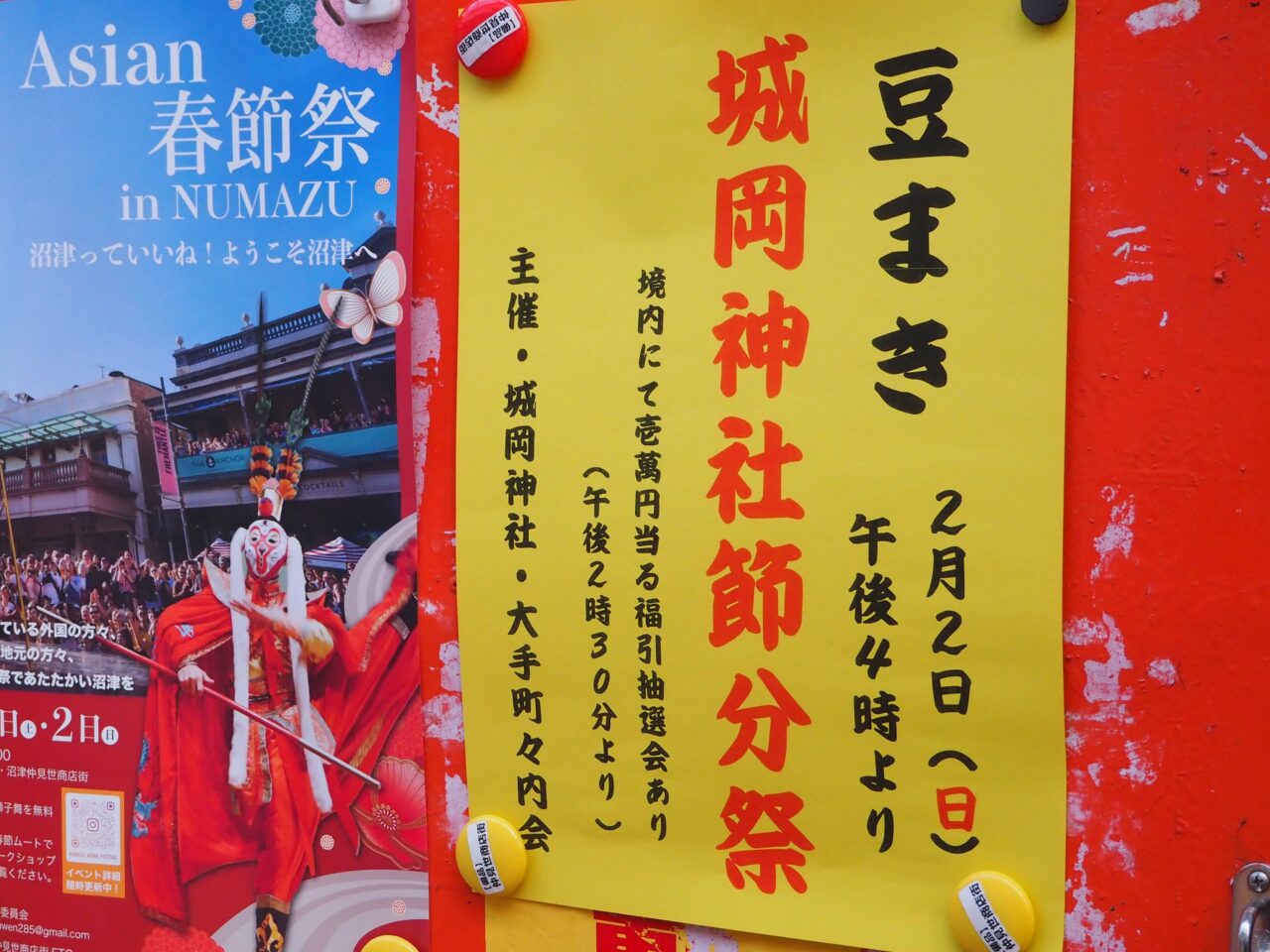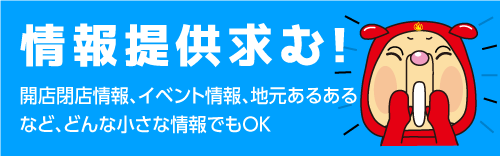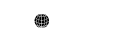【沼津市】ぬまづ観光ボランティアガイド「愛鷹の古墳と湧水めぐり」が開催されました
 ぬまづ観光ボランティアガイドによる自主企画イベント「愛鷹の古墳と湧水めぐり」が、2025年9月21日(日)に開催されました。金岡地区センターを出発・到着地点とし、地域の歴史を学びながら約2時間の散策を楽しみました。
ぬまづ観光ボランティアガイドによる自主企画イベント「愛鷹の古墳と湧水めぐり」が、2025年9月21日(日)に開催されました。金岡地区センターを出発・到着地点とし、地域の歴史を学びながら約2時間の散策を楽しみました。
最初に訪れたのは、西熊堂にある東光庵の遊水池です。三角池とも呼ばれ、古くから「この池の湧水で目を洗うと目の病が治る」と伝えられてきたことが紹介されました。

2024年の秋に国指定史跡になった高尾山古墳
続いて高尾山古墳を見学しました。この古墳は約1800年前、古墳時代初期に築かれたとされ、列島東部において最古級かつ最大級の前方後方墳とされています。2024年秋には国指定史跡となり、今後は古墳の保全と都市計画の両立を図る道路工事が進められることも説明されました。
 民家の合間の道路脇に立っているのは金岡小学校跡碑です。このウォーキングの出発点となった金岡地区センターと隣接する金岡小学校が、かつてあった場所で、当時は桜並木があったことなども紹介されました。
民家の合間の道路脇に立っているのは金岡小学校跡碑です。このウォーキングの出発点となった金岡地区センターと隣接する金岡小学校が、かつてあった場所で、当時は桜並木があったことなども紹介されました。
 江原素六墓も巡りました。江原素六は明治時代の教育家、そして政治家として活躍した人物です。沼津兵学校、集成舎(現在の沼津市立第一小学校)、沼津中学校、駿東高等女学校(現在の沼津西校)や、東京にある麻布中学校も作りました。さらに愛鷹山で西洋式の牧畜を始めたこと、政治家として板垣退助とともに活動したこと、キリスト教の布教にも尽力したことも紹介されました。
江原素六墓も巡りました。江原素六は明治時代の教育家、そして政治家として活躍した人物です。沼津兵学校、集成舎(現在の沼津市立第一小学校)、沼津中学校、駿東高等女学校(現在の沼津西校)や、東京にある麻布中学校も作りました。さらに愛鷹山で西洋式の牧畜を始めたこと、政治家として板垣退助とともに活動したこと、キリスト教の布教にも尽力したことも紹介されました。
 さらに、高尾山古墳の北側にある長塚古墳も訪れました。こちらは高尾山古墳より約300年後、古墳時代後期に築造されたとされます。沼津市内に残る3基の前方後円墳の中で、最も完全な形を保つ古墳です。
さらに、高尾山古墳の北側にある長塚古墳も訪れました。こちらは高尾山古墳より約300年後、古墳時代後期に築造されたとされます。沼津市内に残る3基の前方後円墳の中で、最も完全な形を保つ古墳です。
 参加者からは「歩いてみることで、普段とは違った景色が見られました」との声が寄せられました。古墳時代から近代日本に小学校が誕生した頃にも、この地域には多くの人たちが暮らしていたことを実感したイベントになりました。
参加者からは「歩いてみることで、普段とは違った景色が見られました」との声が寄せられました。古墳時代から近代日本に小学校が誕生した頃にも、この地域には多くの人たちが暮らしていたことを実感したイベントになりました。
訪問場所の一つになっている長塚古墳はこちら↓